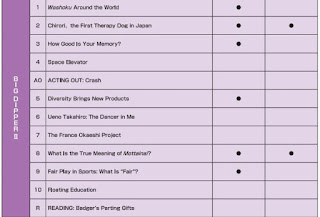大阪梅田のスタジオにおいて,高校用英語検定教科書Big Dipper English Communication(Book 2)のための音声教材録音を行いました。
教科書サイト
https://www.chart.co.jp/goods/kyokasho/30kyokasho/eigo/data/dipper-com.pdf
収録では,特に新出単語について,教科書が規定する標準発音と実際の母語話者ナレーターの発音が一致しているかどうかを確認します。
たとえば,OKについて言うと,アクセントをオウとケイの両方に均等に置く場合,前に置く場合,後ろに置く場合などがあります。
ジーニアス英和
研究社英和中
もちろんアクセントは文脈によって変化するわけですが,辞書の第1記述を仮に標準発音とするならば,ジーニアスに従えば均等アクセントで,英和中に従えば後ろアクセントで収録することになります。母語話者はある種の感覚というかフィーリングで発音しますので,様々な齟齬が出てきます。収録ではこうした細かいチェックをすべての語について行いますので,ナレーターにとっても,音声監修者にとっても,精神的に消耗する作業です。
もう1つ,よくある問題が,強勢の置かれた母音の「ア」の音です。
ジーニアス英和
研究社英和中
この場合,ジーニアスに従うと「カーンサントレイト」のような発音に,研究社に従うと,「カンサ(ス)ントレイト」のような音になります。たしかに非常に強い強勢を置くとそんな音になるのですが,ナレーターは,単語を単独で発音する場合,そこまで強勢をはっきり意識しません。そのため,結果として,「"コ"ンセントレイト」(コに少しアクセント)のような音になります。この場合,どこまで辞書の基準に合わせて取り直すのか,非常に悩ましい判断です。